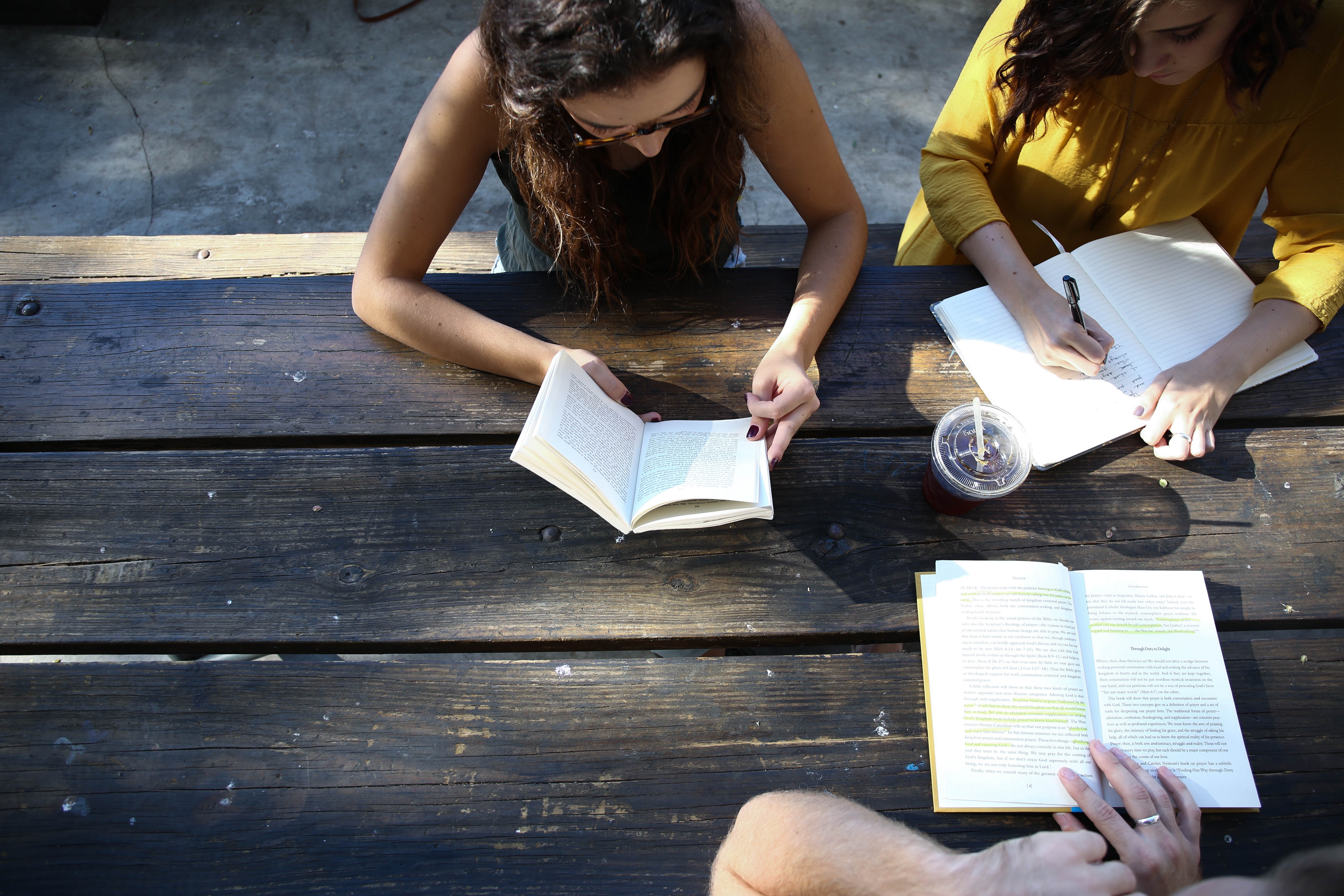足を骨折すると歩けなくなって生活が一変します。歩けることのありがたさを感じる感じますね。
骨折してから1ヶ月以上足を床につけない生活を続けてきました。
足が細くなって右と左の差がすごいです。
手術をしてから6週目に入ろうとしています。いよいよ待ちに待った荷重訓練(地面に足をつくこと)ができる時期になりました。
久しぶりに足を地面に着くのはどんな感覚なのか?
荷重訓練が始まったらどう変化していくのか?
荷重訓練がはじまると急速に変化します。
どんどん変わっていく足の感覚。
どんな訓練をしたのかを記事にしました。
荷重訓練を開始 はじめは体重の1/3から
これまでのリハビリは週3回を継続してきました。
リハビリとオイルマッサージをして、足首と足指の動きが少しずつ、着実に良くなっています。
でも、さすがに筋肉は細くなりました。体重をかけることができないと筋トレにも限界がありますね。
まだ夕方になると少しむくみもあります。
「早く歩きたいな」という気持ちもありますが、
「いま、毎日が人生の初体験の繰り返し」という新鮮な気持ちも常にありながら過ごしてきました。
主治医から荷重許可がおりた 手術から41日(骨折から45日)
退院後初のレントゲン写真の撮影。
1度転んでとても痛い思いをしたので多少の不安があります。大丈夫だとは思いつつも、、。
病院へ到着してレントゲン撮影。


こんな感じです。釘の数が多い。
骨折した線が脛骨も腓骨もはっきりとしています。でも正しい位置に収まっているようにも見えます。
先生のお話。
レントゲンの画像からズレもないし、骨折の経過は順調です。
傷口も綺麗です。
体重が65kgなので、1/3荷重、だいたい20kgまでの荷重を練習していきましょう。
とのこと。
良かったです。経過は順調みたい。
多少転んでも大丈夫でした。
1/3荷重訓練はどんな感じ?
受診の次の日。いよいよ荷重訓練がはじまります。
訓練初日のリハビリはワクワクです。
訓練は単純でした!
- 座って荷重訓練
最初の訓練は、体重計の数字を見ながら足で押します。
座ったまま右足左足の下に体重計を二つ置きます。押してみてどれくらいが20kgなのかを確かめます。
力が入っているのか?足の裏にかかる体重の感覚がよくわかりません。20kgって言われても数字を見ないとわからない。
6週間足を床についていないと感覚を忘れますね。
けっこうがんばって力を入れている感じ。でも痛みは全然ありません。 - 立って荷重訓練
感覚を確認したあとに、今度は立って同じことをします。
立ってみても、足に力が入っているのかよくわかりません。
やっぱり体重計の目盛りを目で確認しないと感覚はつかみにくい。
骨自体は体重をかけようと思えば、まだまだかけられそう。でも筋肉に力が入らなくて膝がガクッと折れてしまいそう。怖いです。
痛みは全然ありません。
最初は力が入ってる感触が本当に薄い。
リハビリのセラピストに促されて、どこに体重がかかっているのかを確認しました。
小指側に体重がかかって、親指側が踏みにくいです。
床に着いている踵はビリビリしています。内くるぶしの傷口がツッパって、時々バリバリっと痛みが走ります。嫌な痛みではないです。ストレッチされているような感じ。
着実に進んでいる感じはありますが、足の筋肉の衰えを感じました。
筋力トレーニングの大切さを痛感、、
今後は筋トレ大事ですが、まずは使われていなかった神経がこれから目覚めていく段階からはじまります。
時間はかかります。地道に少しずつ続けてみます。
リハビリのセラピストからのコメント
と言われました。(荷重訓練を開始するとそれくらい大きく変化することもあります)
でも、全く痛みは出ませんでした。
外来のお医者さんからのコメント
と言われました。
今後が楽しみです。
1/3荷重訓練 2回目で早くも変化
骨折から47日目
昨日はじめての荷重訓練を体感。すぐに二日続けてリハビリ。
2回目で感じたことは、1回目と2回目では力の入り方が全然違うということでした。
どんな訓練をするのか?リハビリ内容
- 座ったまま20kgまで足の裏を押し付ける
骨に機械的な刺激を与えることと、荷重の感覚を確かめるのに必要な最初の練習。今日も同様です。座ったままだと20kgまではなかなか踏めない。力一杯押す感じ。
足を動かす運動と、体重をかける(支えたり踏み込む)運動は感触が全然違います。 - 座っている姿勢から立ち上がって立位をとる
立ち上がってみます。足首は硬くなっていてスネが前に倒れていかない。
手術の傷(内くるぶしの裏)にはつっぱった感じが強いです。
ツッパっているところをストレッチするような感じで体重をかけていきます。
足の裏は、全体で接地している感触ではなく小指側に勝手に体重がかかります。所々浮いていているような感覚。床につきにくいです。
ゆっくりと行いますが指定されている20kgの加減はやっぱり難しい。 - 平行棒内を歩く
2回目のリハビリでは平行棒内を歩いてみました。全然勝手が違って骨盤を回さないとうまく歩けません。足が動かない。物みたい。
左足の足首がスキーブーツのように感じます。まるで物を扱っているような感覚。骨折している左足を大きく出して、右足はあまり追い越さないで歩きます。
自分でコントロールできるまでは程遠い感じがします。まだまだ筋肉は働いている感じが薄い。
でも、2回目のほうが明らかに立ちやすくなっています。
初日は平行棒で歩くなんて想像できなかったので、うれしい進歩です。
足をついて松葉杖で歩く許可が出た(自宅内では)生活が一気にな楽になる
リハビリのセラピストから、松葉杖を使って、家の中でも足をついて少しずつ歩いてもいいという許可が出ました。
ということは、家の中ではPTB装具を着けなくてもいいということ。
おそるおそる練習開始。
扉を開いたり、ちょっとしたものをかわしたりすることが必要で、ちょっと神経を使います。
でも楽しい。
足がわずかにでも床につけるというのは、一気に行動が楽になります。
装具を着用せずに2本の足で歩けることはすごく嬉しい。
歩けることって素晴らしいですね。良い経験をしました。
移動すること自体が荷重訓練になるので、訓練の効果も加速しそう。

荷重訓練をはじめて5日目 びっくりするほど変化が早い
骨折から50日目
荷重開始5日目。だいぶ荷重することに慣れてきました。
自分の足の裏が地面についている感触がはっきりと実感できるようになってきました。
そしてすごく大きなうれしい変化があります。
足の形がどんどん整っていきます。
足首の動きも良くなっているように感じます。
荷重訓練をはじめてからの変化の早さ、大きさに驚きです。
先生の言っていたことは本当でした。
焦らず、無理をしなくても、できる範囲のことを少しずつやれば体は応えてくれますね。
長い目で見て「丁寧に動かしていくこと」って大事なんだということを勉強させてもらってます。
外来のドクターが言っていたように
「荷重訓練が始まると変わるのが早い」
動かしていなかった筋肉は、最初神経が回復していくので、焦らず刺激を繰り返して!!
5日目からはリハビリがハード
どんな訓練をするのか?リハビリ内容
今回のリハビリから新たな練習を追加。
平行棒内に体重計を置いてランジをしました。
(ランジとは、、左足を前に出して右足は後ろ。左膝を曲げて骨盤を前傾させていきます)
左足に体重をかける怖さもあって、おそるおそるしかできず、、。
また新たな足の使い方なので、ぐらつきます。やはり支えにくい。
リハビリのセラピストに目的を聞いた
「ハムストリングスを働かせて膝を安定させる目的です」とのこと。
僕は元々前屈が硬くて、ハムストリングスが働きにくいと感じていたので、この練習はやりがいがありました。難しいけど楽しい。
でも正直、『5日目にしてもうこんなハードな練習をするのか』と驚きです。
その後のリハビリ
リハビリは外来でのリハビリを週3回継続していきます。
荷重訓練をはじめて1週間でできる練習
- 平行棒での歩行練習
- 立ち上がりの練習
- 立って足の指を踏ん張る練習
- ランジ
- 松葉杖での歩行
いろいろできるようになっていきます。
歩くことにも慣れてきました。
リハビリのセラピストとは、お話だけでも参考になるし、『自分がやっていいこと悪いこと』『経過は順調か』など聞けるので本当に安心できます。
たくさんお話しするといいですね。
荷重訓練をはじめてから気になることをリハビリで聞いた
最近気になることがあったので、リハビリで聞いてみました。
『装具を着用しないで歩くと踵がバリバリ言う』
リハビリの先生によれば、
足は全然痛みはなくて、平行棒内であれば、結構余裕で歩けます。
自宅でできる1/3荷重訓練を簡単にまとめました→
その他の経過
冬の松葉杖にはピックをつける
雪が降りました。外は凍っています。(2017年冬)
松葉杖はめちゃくちゃ滑ります。特にコンビニやスーパーの床は濡れているとツルツル。急に滑るので本当にびっくりします。要注意です。
僕はこの時期に荷重訓練が始まってタイミング的にはまだまだ怖い時期でした。
外で歩く時のために、松葉杖の先にピックをつけてもらいました。装備は重要。外の氷に不安がなくなります。
PTB装具は外で使用
荷重訓練が始まると室内ではPTB装具を着用しなくなりました。
でも外出する時は装具を装着すると心強くて、頼りになっているのは間違い無い。外出時はまだ装具は必要です。
外から不意にぶつかってこられても安心できるので、、。
ポイント
・外出時は必ず装具着用。保護のためにも良い
・自宅内は着用せずに荷重の練習をする
リハビリの効果をアップさせるために自分でできること
リハビリの効果をより向上させるため、骨折の癒合を促進するためには、食事も大切です。
僕は食事で補いきれていないと思い、サプリメントを利用しはじめました。
そして、僕が骨折して唯一といっていいほどの失敗が傷跡のケア。
手術傷跡をきれいに治すには、ケアする方法があります。絶対に傷跡のケアはするべきです。
傷跡をきれいにする方法をご紹介します。
傷跡をきれいに治したい、後遺症をなるべく残したくはずなので、瘢痕ケアをしましょう。
骨折を早く治す方法もまとめてみました。